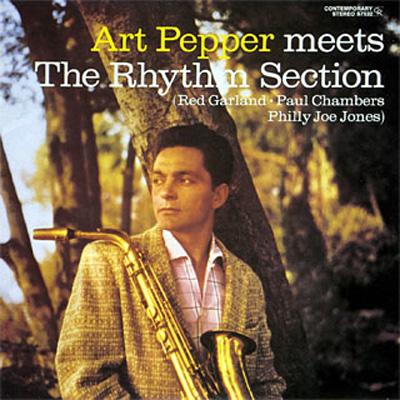|
いわゆるウェストコースト派と呼ばれる。ニューヨークのいかにも薄暗いジャズクラブから聴こえてくるようなヤニっぽいサウンドではなく、あたかもカリフォルニアの青空のような澄み切ったサウンド。ペッパーに代表されるような白人のジャズプレイヤーというものから連想されるイメージは、比較の意味で言う黒人のプレイヤーのイメージとは異質な特徴を持っている。その違いを極端に単純化すれば、「さらっとした感じ/こってりした感じ」「軽やかさ/粘っこさ」「技巧的/個性的」「アンサンブル重視/ソロ重視」。その特徴を一般的には、さらっとした軽やかさが身上の、傾向としてテクニカルでアンサンブルを重視した音楽と言え、それはペッパーのプレイを聴いたイメージに当てはまる。 これだけでは、何か耳当たりが滑らかなだけのBGM的な内容空疎と誤解されてしまいがちだけれど、表面的な軽さの底には、他のプレイヤーには真似のできない独創的な即興演奏を聴くことができる。親しみ易いメロディーのテーマからアドリブに入るや原曲を破壊してしまうほどの凄味のあるプレイが底には隠されている。チャーリー・パーカーとは違った方法論によるもので、ペッパーの特徴は、それだけ凄いプレイを、そうであるかのようには見せないで一見軽やかに演ってしまうことと、メジャー・コードを基本において深刻にならないというところにある。実際に、口当たりの良いメロディをぼんやり聴いているうちに、思いもかけないところに連れて行かれてしまう。まるでハーメルンの笛吹きみたいな恐ろしさを内に秘めていると、私は思う。そして、ペッパーはその豊かな即興フレーズの中のところどころに、スパイスのように、マイナー調のメロディを挿入して、思い入れたっぷりに情緒纏綿と聴かせる、陰影の美を強く感じさせるところがある。いわば、引きの美、なのだ。だから、一度聴いてしまって満腹して、もう沢山というのではなく、何度でも繰り返し聴いても飽きることがない。 活動期間は長いが、1950年代に活躍した後、しばらく麻薬に溺れてブランクがあり、1970年代にカムバックした後は陰影の美は影をひそめパワフルなプレイに変身してしまったと言われる。
バイオグラフィー アット・ペッパーは私生活では華やかだったり大きな困難に直面したりと紆余曲折が大きかったが、レコーディング・スタジオでは、それを持ち込むことはなく、いつも変わらなかった。彼が残した録音は全ては価値あるものだ。アルト・サックス奏者としては、1950年代のチャーリー・パーカーの影響が支配的だった時に独自に自分のサウンドを創造することができた数少ない1人で、他に思いつくのは、リー・コナニッツとポール・デスモンドなど少数にすぎない。晩年の数年間のプレイは、人生の経験を音楽に注ぎ込むような熱さがあった。 彼は若いうちは、ロサンゼルスの中央通りでほとんど黒人ばかりのグループとプレイしていた。兵役を済ませたあとスタン・ケンジントン楽団で過ごした1947〜52年は、彼にとってもっとも幸福な時期だったと言える。もっとも、この時に彼は麻薬中毒になってしまった。1950年代には、リーダーとしてもサイドマンとしても頻繁にレコーディングを行った。その成果が、少なくとも二つの古典となっているアルバム「Plays Modern Jazz Classics」と「Meets the
Rhythm
Section」。1957〜60年でのコンポラリーでの録音が彼の絶頂期だった。しかし、その経歴の前半は突然終わってしまう。1953〜56年に2度の麻薬所持による収監があったが、1960年代を通じて数度の長期間の懲役に服したためだった。その刑期の合間には時折ギグを行うこともあったが、それは彼の長年のファンを困惑させるような、彼のアルトは、それまでとは異質なジョン・コルトレーンの影響の濃厚なハードなプレイに変質してしまっていた。1968年にバディ・リッチとの録音の後、シナノン療養所での数年間のリハビリに努めることとなった。 ペッパーは1975年にカムバックを果たす。妻のローリーの指導と激励により、以前のプレイを取り戻しただけでなく、独自の強烈なソロで自身の最後の輝きを見せたのだった。彼はまた、時折、クラリネットもプレイした。彼のコンテンポラリーとギャラクシーへの録音は彼のキャリアの中でも最も偉大なものだ。 村上春樹はペッパーについて、以下のようなことを書いている。(「ポートレイト・イン・ジャズ」より) アルト・サックスという楽器には、ある種のフラストレーションが影のようにつきまとっている。正確に表現すれば、「そこに本来あるべきものと、実際にそこにあるものとのあいだにあるずれ、齟齬感」ということになるのだろうか。それはたぶんアルト・サックスという楽器の構造に起因するものなのだろう。演奏者が頭に描く音楽の情報量が、アルト・サックスという楽器にうまく収まりきらず、収まらない部分がぼろぼろと端からこぼれ落ちていく─そういう印象を、僕らは受けてしまうことになる。 そのフラストレーションはある場合には文字通りの苛立ちにもなり、またある場合には満たされることのない憧憬のようなものにもなる。あるいはその両者を同時に含むものにもなりうる。そのあたりの切迫性は、テナー・サックスには求められないものだ。テナー・サックスは、アルト・サックスに比べると良くも悪くも自己充足的であり、意志的であり、遥かに堅固なグラウンド上にいる。 そのようなアルト・サックスの「危うさや切迫性」という部分に焦点を絞っていくと、そこには否応なく、アート・ペッパーの姿が浮かび上がってくる。その楽器の持つ生身の刃物のようなぎりぎりさと、その裏側にある架空の楽園の情景を、ひとつの音楽像として克明に、リアルタイムに具現化した演奏者は、彼のほかにはいない。チャーリー・パーカーを、奇跡の羽を持った天使とするなら、アート・ペッパーはおそらくは変形した片翼を持った天使だ。彼は羽ばたく術を知っている。自分が行くべき場所を承知している。しかしその羽ばたきは、彼を約束された場所へとは連れては行かない。 彼の残した数多くのレコードを聴いていると、そこには一貫して、ほとんど自傷的と言ってもいいほどの苛立ちがある。「俺はこんな音を出しているけれど、俺が本当に出したいのは、これじゃないんだ」と、彼は我々に向かって切々と訴えかけている。彼の演奏には、それがどれほど見事な演奏であったとしても、ソロが終わった直後に、楽器をそのまま壁にたたきつけてしまいそうな雰囲気がある。僕らはアート・ペッパーの演奏を愛する。しかし彼の残した手放しに幸福な演奏を、僕らはひとつとして思い出すことができない。彼は一人の誠実な堕天使として、自らの身を削って音楽を創り出していたのだ。そしてアルト・サックスは与えられるべくして彼に与えられた楽器だったのだ。
|
 1925〜1982年 カリフォルニア州ガーディナ生まれ
1925〜1982年 カリフォルニア州ガーディナ生まれ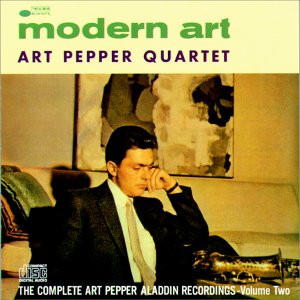
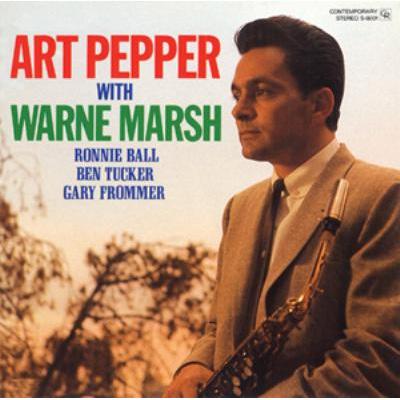 I Can't
Believe That You're In Love With Me (Orig.
Take)
I Can't
Believe That You're In Love With Me (Orig.
Take)